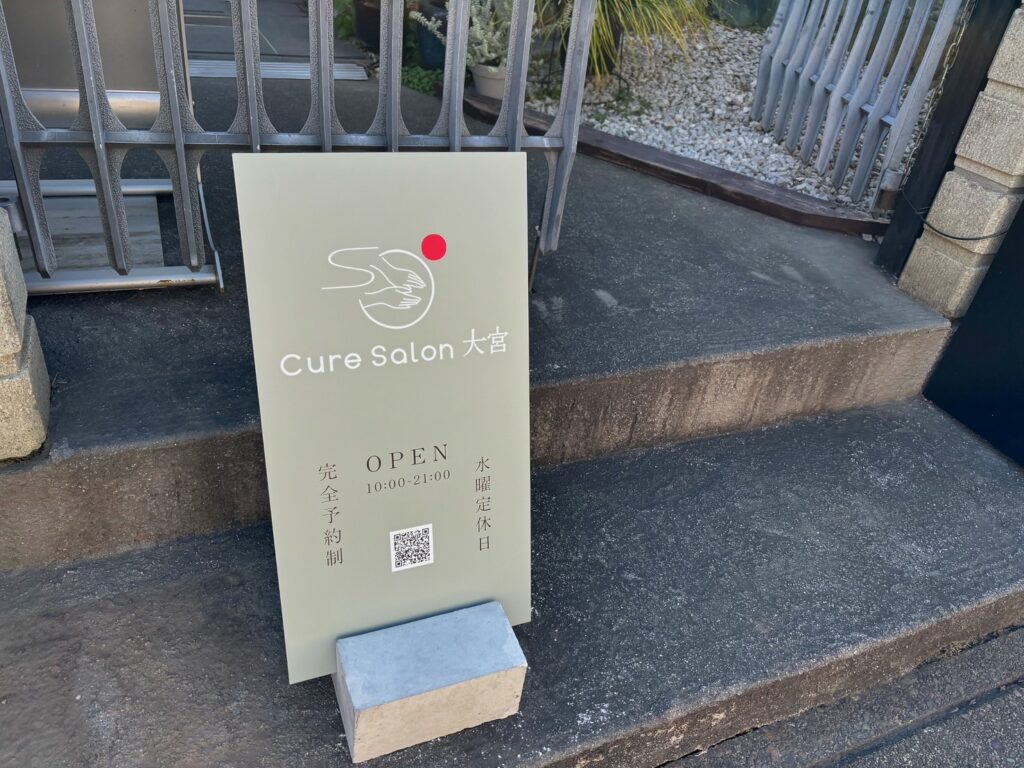小さな炎症と慢性炎症

CureSalon大宮 荻島です。
最近、保険会社のプルデンシャル生命のメールマガジンにて炎症をテーマにした以下文章が紹介されました。
とても素晴らしかったので紹介します!!是非すべて読んでみてください。
大まかに補足の上まとめると、「呼吸の大切さと腸内環境や免疫」「体の柔軟性」といったところかと思います。
体の柔軟性は顔や首、足首手首、脊柱に焦点を当てたやり方を少しでも、温熱後に行えれば最良かと思われます(^^♪
ぜひご参考にしてみてくださいね。
炎症というと、「赤く腫れて熱を持った状態」をイメージする人が多いことでしょう。医学的にも、炎症とは発赤(赤くなる)・熱感(熱い)・腫脹(腫れる)・疼痛(痛み)のある状態とされます。
ところが、こうした目に見える炎症だけではなく、「目に見えない炎症」もあります。肉眼では確認できず、通常の検査でも発見しにくいこの炎症は、25年ほど前から医学界で認識され始めました。熱も腫れも痛みもないのに、体内では静かに異常が進行しているのです。軽微であるがゆえに軽視されがちですが、だからこそ厄介です。
一般的に炎症は、身体を守るための免疫細胞の闘いが、正常に行われている証です。たとえば、傷から感染して、その部分が腫れて熱を持っているとき、内部では侵入した細菌などの病原体と免疫細胞が闘っています。通常は、免疫細胞が無事に勝利を収め、病原体が排除され、炎症が起こった部分が修復されて、もとに戻ります。これは、目に見える炎症であり、「急性炎症」といいます。
一方、目に見えない炎症が厄介なのは、急性炎症とは異なり、軽微な炎症が治りきらないまま、くすぶり続けることがあるからです。これを「慢性炎症」といいます。
また身体の一箇所でも慢性炎症があると、そこから出る炎症物質(サイトカイン)が全身へと波及します。たとえば、腸の慢性炎症が全身の疲労感や関節痛を引き起こしたり、歯周病や虫歯から心臓病が起こることもあります。さらには、メタボリックシンドロームや糖尿病などの生活習慣病、アルツハイマー病やがん、自己免疫疾患にも慢性炎症が関係しているともいわれます。
つまり、見えない炎症は、大病の前触れである可能性がある、ということです。自覚症状がないからといって放置すれば、体は静かに蝕まれていきます。
POINT
慢性炎症は目に見えず自覚しにくいが、生活習慣病やがんなど重大な疾患の原因になる。放置してはいけない
腸のコンディションが健康の基盤
ここでは例として、腸の慢性炎症を取りあげます。健康への第一歩として、まずは腸内環境の見直しから始めてみましょう。現代人の多くが、慢性的な腸の炎症に無自覚であり、それが不調の温床になっているといわれています。まずは簡易チェックをしてみましょう。
チェックが多いか、★印にひとつでも該当するものがあれば、要注意です。
【腸の慢性炎症】が関わる可能性がある症状・状況
・★お腹の張り、便秘、下痢などの腸トラブルが多い
・お腹まわりの脂肪が多い
・アレルギー症状や自己免疫疾患がある
・★たびたび抗菌薬(抗生物質)を使用してきた
・薬をたくさん飲んでいる
・加工品、添加物の摂取が多い
・小麦製品、乳製品の摂取が多い
・野菜をほとんど食べない
・電子レンジをよく使う
・砂糖や甘いものの摂取が多い
・マーガリンや油を含むお菓子、スナック類などをよくとる
・お腹いっぱい食べないと気がすまない
・食事の時間が不規則。夕食が夜8時以降になる
・胃もたれ、消化不良に悩まされる。お腹がすくことがない
腸壁には絨毛(じゅうもう)とよばれる毛のような器官が敷き詰められていて、絨毛の表面には上皮細胞があります。上皮細胞は、栄養素を吸収しつつ、一定以上の大きさの異物の侵入を防ぐフィルターの役目を果たしています。また腸内細菌や粘液も異物の侵入を防ぎます。
ところが炎症が起こると、上皮細胞同士の結合が緩みます。また粘液による防御機能が低下し、腸内細菌のバランスが乱れるため、フィルターがうまく働かなくなります。こうなると、体内に不要なものが侵入してしまうのです。
それでは、腸の炎症を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。「超加工食品」と「白砂糖」が、炎症を起こしやすい食品で、具体的にはハムやウインナー、練りものなど、素材がわからない加工食品は極力避けるべきと著者は記します。反対に、炎症を起こす心配が少ないのは、野菜、海藻、良質な肉や魚、卵、豆類、ご飯、いも、そばなどです。刺身、焼くだけ、みそ汁、野菜なら洗って切るだけなど、手間のかからない料理で十分です。
POINT
腸が炎症を起こすと不要なものが体内に侵入してしまう。超加工食品を控え、野菜や魚など自然な食事を心がけること
「空気の関門」の不調が病気の原因に
のどや口も、慢性炎症を起こします。まずは次のチェック項目に心当たりがあるか確認してみてください。
【上咽頭・口腔の慢性炎症】が関わる可能性がある症状・状況
チェックが多いか、★印にひとつでも該当するものがあれば、要注意です。
・★のどの違和感や痛みがある
・鼻づまりや後鼻漏(鼻汁がのどの奥に落ちていくような症状)がある
・原因不明の痰や咳が続くことがある
・歯の知覚過敏や多歯痛(多くの歯が同時に痛む)、舌の痛みがある
・頭痛や顎関節痛(あごの痛み)、ひどい肩こりや首こり、手や指の関節痛がある
・口で呼吸することが多く、口のなかが渇きやすい(特に朝)
・砂糖や甘いものの摂取が多い
・歯磨き(ブラッシング)が不十分になりがち。歯科の定期検診を受けていない。虫歯がある
・歯肉炎や歯周病(歯槽膿漏)・口臭がある
・★扁桃炎(のどカゼ)や副鼻腔炎のような症状を繰り返す
・子どもの頃から、鼻炎やぜんそくなどがあった
・いびきをよくかく。呼吸が止まっていると家族に指摘される
特に最近注目されているのが「慢性上咽頭炎」です。上咽頭とは、のどの上部で鼻の奥に位置する部位です。中咽頭・下咽頭は、口のなかと同じ丈夫な扁平上皮で覆われていますが、上咽頭だけは粘液を分泌する絨毛上皮細胞でできています。この粘液と絨毛の働きにより、空気中の病原体や異物は痰として体外に排出される仕組みになっています。また、上咽頭にはリンパ球も豊富に存在し、免疫の最前線として機能しています。
著者は「腸が、食品とともに入ってくる異物を排除する関門なのに対し、上咽頭は、空気とともに入ってくる異物を排除する関門」と書いています。この重要な部位に慢性的な炎症が起きることで、のどの違和感、痛み、後鼻漏、長く続く痰、歯の知覚過敏、多歯痛、舌痛、顎関節痛、首肩こり、耳鳴り、頭痛などが起こりやすくなります。また上咽頭は自律神経や免疫機能とも密接に関連しています。そのため、全身倦怠感、めまい、起立性調節障害、記憶力、集中力低下などの症状が起こりやすくなり、免疫関連の病気としてはIgA腎症、ネフローゼ症候群などに慢性上咽頭炎が深く関わっているとされます。
慢性上咽頭炎の対策として、すぐに取り組めるのが「口呼吸をやめる」ことです。本来、呼吸は鼻が担うべきです。鼻腔内の構造は空気を温め、加湿し、異物を除去する機能を備えています。口呼吸ではこれらの機能が失われ、冷たく乾いた空気が直接のどを刺激し、炎症を引き起こしやすくなるのです。
まずは、意識的に口を閉じるようにしましょう。そして「あいうべ体操」で口まわりの筋肉を鍛えると、口呼吸の癖が自然と減少します。「あー」「いー」「うー」「べー」と発音するだけの簡単な運動ですが、「うー」は口を前に突き出し、「べー」では舌をしっかり突き出すのがポイントです。